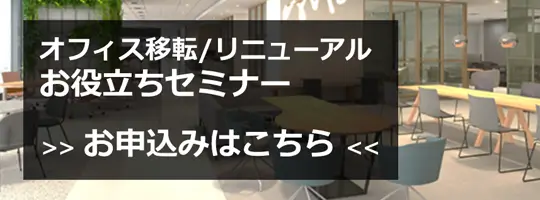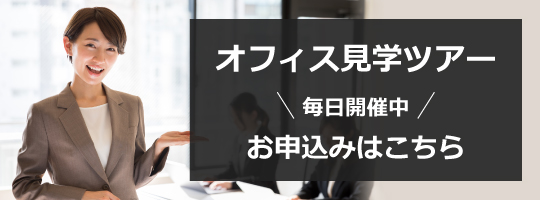感染原因の多くを占める接触感染に効果的なデルフィーノ! デルフィーノってなに?施工方法は?導入費用はどのくらい?実績は? などなど、初めての方にも分かりやすくまとめました
職場クラスターの発生は、企業にとって深刻な問題です。感染が拡大すると、従業員の健康だけでなく、企業の業績や信頼性にも大きな影響を与えかねません。従業員の安全を確保するには、適切な予防策を講じるだけでなく、潜在的なリスク要因に対しても対応策を準備する必要があります。
今回は、職場クラスターを回避するための具体的な手段や企業の責任、押さえておくべきリスク要因について解説します。必要な対策やオフィスで徹底しておきたい接触感染防止策について理解を深めましょう。
目次
職場クラスターとは

新型コロナウイルスの流行を経て「クラスター」という言葉を耳にするようになりました。職場クラスターを発生させないために、企業はさまざまな対策を講じる必要があります。はじめに、職場クラスターの定義と職場クラスターが発生してしまった場合の企業責任について確認しておきましょう。
職場における「クラスター」の定義
クラスターとは「群れ」や「集団」を指す言葉です。新型コロナウイルスなどの感染症におけるクラスターとは「小規模の集団感染」や「特定疾患にかかっている人が一定数以上集まった状態」を指す言葉として使われます。
「小規模」や「一定数以上」の目安については、厚生労働省の定義によると「当面の間接接触歴等が明らかとなる5人程度の発生」とされています。
職場クラスターが発生すると企業が責任を問われる?
職場クラスターが発生すると、企業は法的責任を追及されることがあります。そのポイントとなるのは「安全配慮義務」をクリアしているかどうかです。
安全配慮義務とは、雇用主である企業が従業員の健康と安全を確保するために負う法的責任です。企業は、労働環境を安全かつ健康的な状態に維持し、必要な安全装置や設備を整備し、適切な指導や教育を提供しなければなりません。また、従業員が危険な状況にさらされないように予防措置を講じることも含まれます。
したがって、職場クラスターが発生した場合には、従業員が感染しないように密を避ける環境を作っていたか、定期的に職場の換気を行っていたか、マスクの着用や手指消毒を徹底させていたかなど、感染対策が十分だったかが問われることになります。
会社の感染対策が不十分だったと判断された場合には、訴訟に発展することもあり得るため注意が必要です。
クラスター発生につながる主なリスク要因
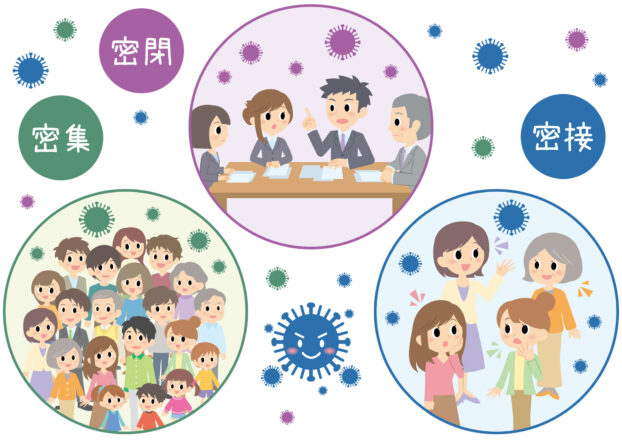
クラスターが発生しやすい場所には、一定の条件があります。職場クラスターを回避するためには、まず、そうした状況を作り出さないことが必要不可欠です。どのような状況下でクラスターが発生しやすいのか、具体的に見ていきましょう。
3密(密閉・密集・密接)環境
厚生労働省による注意喚起では、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」の「3密」の回避が強調されています。実際に、クラスターの発生は、この3つの密が原因となっているケースが多いのが実情です。
クラスターが発生しやすい場所としては、具体的に以下のようなものがあります。
・病院
・カラオケボックス
・職場の会議
・スポーツジム
・接待を伴う飲食店
・バスツアー
・学校
・幼稚園や保育園
・福祉施設
上記の場所は、それぞれ特有の感染リスクがあります。たとえば、大音量が流れている環境では自然と声が大きくなり、飛沫感染のリスクが高まるでしょう。介護施設や病院、幼稚園、保育園などでは、他者と接触する機会が多く、症状が出ていないウイルス感染者が無意識に感染を広げている可能性があります。また、学校なども長時間同じ空間に滞在することから、クラスターが発生しやすい場所の1つです。
基本的感染対策の不足
クラスターが発生した場所では、基本的な感染対策が不足しているケースが多く見受けられます。下記は、クラスター発生につながりかねない感染対策不足の一例です。
・マスクやフェイスシールドを着用していない
・人や場所の消毒が不十分
・換気が不十分で頻度が少ない
・有症状者の見逃し
いずれも現在ではごく一般的な対策であり、徹底されるべきことです。しかし、わずかな気の緩みや条件が重なることによって、クラスターにつながる可能性があります。
オフィスで接触感染対策が必要な背景

オフィスも複数人が長時間にわたって滞在します。前述のクラスター発生場所と共通する要素も多く、感染リスクが高いことを常に意識した対策が不可欠です。
接触感染の危険性
オフィスでのクラスター対策では、とくに「接触感染」に注意が必要です。「接触感染」とは、ウイルスが付着した物に触れて感染することを指します。接触感染の感染源となるのは、唾液や分泌物、体液、排泄物などです。
気をつけたいのは、感染者に直接触れる以外にも、間接的な接触による感染拡大の恐れがあることです。たとえば、ウイルスに感染した人が触れたドアノブやスイッチ、手すりなど日常的に触れるものから感染のリスクが高まる場合もあります。
接触感染では、ウイルスは皮膚から侵入するのではなく、ウイルスが付着した手で顔や髪を触ることで口や鼻、目の粘膜から体内に侵入します。人は無自覚のうちに自分の顔や髪に触れているため、手指の衛生管理が重要です。
オフィスで発生する接触感染の例
オフィスには、複数の人が触れる箇所が数多くあります。一般的に、接触感染のリスクが高いとされている箇所の例は次のとおりです。
・共用PCやデスク
・共用機器(固定電話やコピー機など)
・共用キャビネット
・ドアノブや各種スイッチ
・トイレや休憩スペースなどの共用施設
コロナ禍以前は、無意識に触れていた箇所にもウイルスが潜んでいる可能性があります。これまで以上に衛生意識を高める必要があり、オフィスでの感染拡大を防ぐためには、「感染しない」「感染源とならない」という意識をもち、行動することが大切です。
- 1
- 2