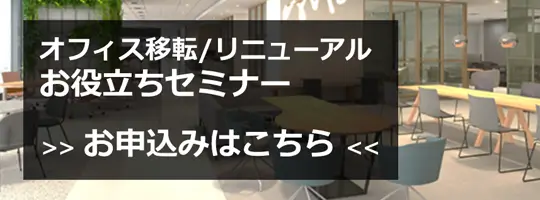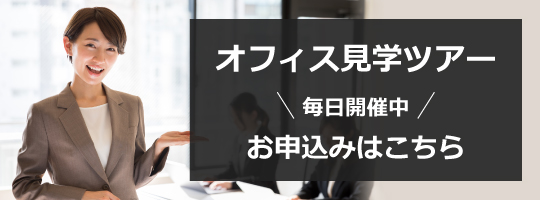「日経ニューオフィス賞」を受賞したコニカミノルタがデザインしたオフィス事例をまとめた一冊です。最新のトレンドが知りたい!新しいオフィスのアイデアが欲しい場合などにご活用ください。
人員の増減や業態変更に合わせて、オフィスレイアウトの変更を検討することもあるでしょう。しかし、オフィスのレイアウト変更は度々あるものではありません。そもそもどこから手をつければよいのか、どのような業者に頼めばいいのか、費用はいくらぐらいかかるのかなど、わからないことが多いものです。今回は初心者だからこそ知っておきたいオフィスのレイアウト変更の基礎知識をまとめました。
目次
オフィスレイアウト変更の基本的な流れ

オフィスのレイアウトを変更するにあたり、まずは流れを確認しておきましょう。企業個別の事情によって異なる部分もありますが、一般的には次のようなステップで進めます。
1. 目的やレイアウトのコンセプトを決定する
オフィスのレイアウト変更は細かい確認や作業が必要であり、状況次第で判断に困るケースも出てきます。そうした作業を効率よく進めるためには、「そもそもなぜレイアウトを変更するのか」「どのようなオフィスにしたいのか」といった目的やコンセプトを明確にしておかなければなりません。最終的なゴールが明確であるほど、後のステップで一貫した判断ができるようになります。
2. 業者を選定する
目的とコンセプトを決めたら、それを形にしてくれる業者を選定します。業者によって価格だけでなく、企画力やデザイン性、請け負える範囲が異なることもあり、業者選びは難航するかもしれません。総合的な視点で検討が必要になりますので、業者に求める要件を事前に決めておきましょう。具体的には提案依頼書(RFP)を作っておくことをおすすめします。
コニカミノルタジャパンは提案依頼書(RFP)の作成方法やポイント、記載項目チェックリストをまとめた資料をご用意していますので、ぜひご活用ください。
▶成功するオフィスづくりの第一歩!提案依頼所(RFP)作成マニュアル
3. 業者と打ち合わせ・最終見積もりと発注
業者を選定したら、いよいよ発注です。ここでポイントになるのは、発注前に業者と認識共有をするための打ち合わせをしておくことです。「業者選定時に要件を提示しているし、あらためて認識共有する必要はあるのか」と思うかもしれませんが、細かい部分の認識齟齬が大きなトラブルにつながるケースもあります。
4. やるべきこととスケジュールの確認
やるべきことを業者と相談しながら、タイムスケジュールとともにToDoリストを作成しておきましょう。誰が何に責任をもつのかを明確にしておくことでトラブルを防げます。業者からの提案を受けるとよいかもしれません。経験豊富で信頼できる業者であれば、細かい部分まで漏れなく整理してくれます。
5. レイアウト変更を実施
発注やToDo確認が終わったら、いよいよレイアウト変更の工事に入ります。工事期間中はオフィスに人が入れない期間があったり、業者の出入りも激しくなったりするため、事前に社員やビル管理会社へ連絡して調整をしておきましょう。また、レイアウト変更後に社員がスムーズに勤務できるよう、オフィスマップや座席表など、社内周知もしっかり準備しておくことをおすすめします。
オフィスレイアウト変更にかかる費用の目安

次に気になるのが費用です。限られた予算のなかでスムーズなレイアウト変更を実施するためにも、おおよその目安を知っておきましょう。
一般的なオフィスレイアウトの変更費用
オフィスの規模や工事内容、委託範囲によって費用は異なりますが、一般的な相場は設計に20万~50万円、内装工事費として坪単価10万~30万円程度(一例として30坪のオフィスであれば350万〜500万円程度)が相場となっています。内装工事はオフィス規模が大きくなるほど坪単価も高くなる傾向があるため、事前の見積もりが欠かせません。
コストに見合った業者選びをするには?
複数業者から見積もりを取得し、価格を比較したうえで業者を選びます。ただし、価格の低さだけを選定基準にするのは危険です。業者を選定する際には、金額と委託内容が見合っているか、求めるクオリティを実現できる内容になっているのかを踏まえて、選定することをおすすめします。たとえば、デザインや工事だけを請け負う業者は安価かもしれませんが、課題解決の視点に立てば、価格が多少高くても事前にコンサルティングを行う業者の方が安心かもしれません。
- 1
- 2